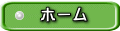歎異抄 第一条【注釈版本文】
弥陀の誓願不思議にたすけられまゐらせて、
往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんとおもいたつこころのおこるとき、
すなわち摂取不捨(せっしゅふしゃ)の利(り)益(やく)にあづけしめたまふなり。
弥陀の本願には、老少・善悪のひとをえらばず、ただ信心を要とすとしるべし。
そのゆゑは、罪悪深重・煩悩熾盛(しじょう)の衆生をたすけんがための願にまします。
しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、念仏にまさるべき善なきゆゑに。
悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑにと云々。
【意 訳】
阿弥陀仏の誓願の思議を絶したおはからいに救われて、
往生をとげさせていただくと信じて、念仏を申そうと思いたつ心がおこる、
そのとき、すでに阿弥陀仏は大悲の光明の中におさめ取りたまい、
決して見捨てぬという救いの利益にあずからしてくださいます。
阿弥陀仏の本願には、老人も若者も、善人も悪人も、いかなる人もわけへだてなさいません。
ただその本願の救いをはからいなく領解する信心が肝要であると知るべきです。
本願が老少、善悪をへだてたまわないということは、深く重い罪悪をもち、
もえさかるほのおのような煩悩をかかえて生きる人をもらさずに救うためにおこされた誓願であらせられるからです。
ですから本願を信じたうえは、救われるために他のどのような善行も必要としません。
如来よりたまわった本願の念仏にまさるほどの善はないからです。また悪もおそれるに及びません。
阿弥陀仏の本願の救いをさまたげるほどの悪はないからである、と仰せられました。
〈第一条〉誓願の不思議
この第一条には、浄土真宗の法義のすべてが要約されています。こんなに簡潔に、しかも感動的に見事に真宗を語りつくされたことばは、
親鸞聖人ご自身の著作の中にも見あたらないほどです。
はじめに、阿弥陀仏の絶対不可思議の誓願力によってわたしのうえに救いがもたされるありさまを、信心を念仏と摂取の利益をもって語り、
ついで本願の絶対平等の救いは、罪深きものを救うためのものであって、
大悲の焦点はつねに煩悩具足のわれらのうえにあわせられていることをのべ、
われらをただはからいなく本願を信受するばかりであるとのべらます。そして最後にこのような本願の絶対的な救済力の前には、
いかなる善もほしからず、悪をもおそれなしといい切り、人間的な価値の世界を超えた絶対無限の領域のあることをはっきりと示される法語です。
▼法蔵菩薩が師仏の教えにしたがったゆえの「誓願不思議」
「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて往生をばとぐるなり」というはじめの一句には、
まず浄土真宗の本体がはっきりとうち出されています。親鸞聖人は『選択(せんじゃく)本願は浄土真宗なり』といい、
浄土真宗とは、阿弥陀仏の選択(せんじゃく)本願を本体としている宗教であると示されています。
その不思議の誓願の始終をくわしく説かれた教典が『大無量寿経』であります。
『経』によれば、久遠の昔、一人の王国が、世自在王仏という如来の教えを聞いて感動し、国と王位をすてて無一文の修行者となり、
法蔵と名のっていったといわれています。古代において国王とは、権力と権威と財力を独占する最高のものでした。
すべての人が血眼になって、身も心もすりへらすようにしてあくせくしているのは、名誉欲と所有欲と支配欲を満たすためですが、
国王とは、それを一手に修めているものです。その王位を破れ草履をすてるようになげ捨てて、出家したいということは、
仏道が開示する真実の領域は、世俗のすべてを捨てても悔いのないほど充実した境地であることを告げようとしているのでしょう。
そしてまた真実の生き方は、世俗の価値体系を、一度は否定しなければ実現しないことをあらわしているともいえましょう。
ところで「法蔵」という名は、「ダルマーカラ」の訳語ですが、ダルマとは「法」すなわち真理のことであり、
「マーカラ」とは「出生するところ」「源」「蓄積」の意味です。つまり「ダルマーカラ」とは、真理を蓄積し、出生する、
みなもとであるような方であることをあらわしています。したがって「法蔵」とは、普通の人間の修行者ではなくて、
内にたくわえている絶対の真実を、本願の始終をとおして、開きあらわし、万人に知らしめ、
真理を万人のものたあらしめていくような方であるという意味をあらわす名なのです。
親鸞聖人は『唯信鈔文類』に次のようにのべられています。
この一如のかたちをあらわして、方便法身と申す御すがたをしめして法蔵比丘となのりたまひて、
不可思議の大誓願をおこして… 。
『唯信証文意(ゆいしんしょうもんい)』
愛と憎しみの対立を超え生と死のまどいを超えた真実一如の世界が、愛欲におぼれ、怨憎(おんぞう)に狂い、
生と死に悩む人々をよびさまし救うために、大悲をこめて近づいてくださったすがたを方便法身(ほうべんほっしん)といい、
誓願が成就して、願いのままに万人を救いたまうすがたを阿弥陀仏というといわれるのです。
修行者、法蔵は、師仏の教えをうけて、あらゆる仏陀たちの世界をみそなわし、五劫という、
人間の思量(しりょう)を絶した時間をかけて思惟し、すべての仏陀たちがなそうとしてなしえなかった、
善悪、賢愚(けんぐ)をえらばぬ万人平等の救いを実現するために四十八種の誓願をおこし、
さらに永劫(ようごう)のあいだ修行して万人の救い主、阿弥陀仏となっていかれたと説かれています。
▼大悲の願につつまれて「往生をばとぐるなり」の充実
その誓願の一々は「たとひわれ仏を得たらんに‥‥もししからずは正覚をとらじ」という定型句で説かれています。
この願いをはたしとげることができなかったら仏陀になるまい、という修行者としての生命をかけた力強い誓願がのべられているのです。
このように、自らのさとりと、悩めるすべての人びとの救いをめざしてかぎりなく修行をつづけていくひとを菩薩とよびます。
目覚めの完成をめざすものという意味です。こうして法蔵と名のる菩薩が、阿弥陀仏となられたということは、
ここに誓願されているとおりに万人を救う絶対的な救済力を完成されたということをあらわしています。
阿弥陀仏とは、万人に救いをつげる言葉なのです。
いま
「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて往生とぐるなりと」といわれたとき、
その誓願とは、広くいえば四十八願を指していますが、
まさしく指すところは、第十八番目に誓われた第十八願といい習わしている次の本願です。
たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽(ししんしんぎょう)して、わが国に生ぜんと欲(おも)ひて、
乃至十念(ないしじゅうねん)せん。もし生(しょう)ぜずは、正覚(しょうがく)を取らじ。
ただ 五逆と誹謗正法(ひぼうしょうほう)とをば除く。 「大経」
たとえわたしが仏になりえたとしても、十方の世界にあって、さまざまな悩みにまつわられつつ生きるすべてのものが、
わたしの救いにうそいつわりのないことを(=至心)疑いなく信受して(=信楽)わが国(=浄土)に
生まれることができるとおもいさだめ(=欲生我国)、たとえわずか十編であっても、念仏申しているのに、
もし浄土に生まれさせることができないようならば、私は正しくめざめたもの(=阿弥陀仏)になりますまい。ただ五逆を造って恥じず、
仏法を否定しつづけるようなものは、このかぎりではない、と誓われているのです。
この広く深い願い、力強い誓いのみことばのなかに、私ども一人一人に向かって、真実に背をむけ、仏法を謗る心をひるがえして、
我が救いを信じ、わが名を称えつつ、わが国に帰りきたれと、大悲をこめて召還しつづけていたまう永遠ないのちのみ声がひびいてまいります。
このいのち、いずこより来たり、去っていずこに往(ゆ)こうとするのか、知りようもない深い混沌(こんとん)の闇におびえる私の人生も、
この誓願のみことばをたまわって、生の依(よ)るべきところを知らされ、生(せい)の帰すべきところを聞きひらくことができるのです。
そのときはじめて、生きることの意味と方向性が与えられるのです。阿弥陀仏の大悲の願いにつつまれ、そのみ名を称えながら、
「往生をばとぐるなり」と言い切らせていただくところに、生と死にゆるぎなき安住の地が確認されていきます。
晩年の良寛に
不可思議の弥陀のちかいのかなかりせばなにをこの世の思い出にせん
という歌がありますが、弥陀の誓願にあいえた人のみの感じる人生の深い充実感があふれています。
◇お念仏によっていざなわれる深い安らぎの世界
親鸞聖人の心の軌跡をあざやかに綴る『歎異抄』―この書の語りかけに、
人々は生きるということの意味と方向性を与えてきたのではないでしょうか。前回は、本書と書名と序言において、
浄土真宗の正意からはずれた異端に対する著者の悲しみと嘆きを、続いて第一条では、
わたしに救いをもたらす「弥陀の誓願不思議」の意味についてうかがいました。
今回は、その誓願のみことばを信ずることによって、展開していく世界について考えてみましょう。
▼信心ー如来の願いが、このわたしにとどく
専精院鮮妙師は『歎異抄』第一条のはじめの一段の読み方について
「弥陀の誓願不思議にたすけられまゐらせて、往生をばとぐるなり」で区切って、
それから声を改めて「と信じて念仏申さんとおもひたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあづけしめたまふなり」と読め、
と注意されています。普通の句読点とはちがうかもしれませんが、そう読むとたしかによく意味がわかるようです。
「弥陀の誓願不思議にたすけられまゐらせて往生をばとぐるなり」というのが、信の内容だからです。
前号で阿弥陀仏の誓願とは、生きとし生けるすべてのものにむかって
「至心に信楽して、我が国に生まれんと欲うて、乃至十念せんに、若(も)し生れずば、正覚(しょうがく)を取らじ」
と願いをかけられてることだといいました。それは、「おねがいだから、ほんとうに(至心)、疑いなく(信楽)、
我が国に生まれることができるとおもい(欲生我国)、たとえ十遍でも念仏をもうしておくれ(乃至十念)」という慈愛をこめた願いです。
親鸞聖人は、この本願のみことばを
「如来、諸有(あらゆる)の群生を招喚したまふの勅命なり」と領解されました。
生きてあることの意味も知らず、命の行方も知らずに迷いつづけている愚かな私にむかって、
生死の彼方から「至心(ししん)に信楽(しんぎょう)して、わが国に生まれんと欲(おも)へ」
大悲をこめてよびかけておられる大悲招喚のみことばであるといわれるのです。
如来のこの招を真実とうけいれ、みことばのままに「わたしには何一つみさだめることができませんが、あなたのおおせにしたがって、
浄土に生まれさせていただく身であると、疑いなく思い定めさせていただきます」とおせにしたがうことを信心というのです。
親鸞聖人が
「信は願より生ずれば 念仏成仏自然(じねん)なり」といわれたように、
信心とは、如来の願いが、わたしにとどいたことですから、
「如来よりたまはりたる信心」(歎異抄)ともいわれました。
▼念仏ー親が子をよび、子が親をよぶ声
本願にはつづいて「乃至十念せよ」と願われています。「お願いだから念仏してくれよ」といわれるのです。
「乃至」とは、念仏の数量を限定しないことをあらわしているから、本願の念仏には「十遍」に限定しないことを知らそうとされているのです。
短命のものは、わずか一声でいのちが終わるかもしれませんし、長命のものは幾万億編も称えることができるでしょう。
しかし念仏は数の多少が問題なのではなく、おおせのままに仏のみ名を称えつつ生きていることが尊いのです。
親鸞聖人は『浄土和讃』の「勢至讃」のなかで、念仏とは、子が母を慕いその名をよぶようなすがたであるが、その根源には、
衆生を一子(ひとりご)のようにかけがいのない大切な仏子として憐れみ念じたもう仏の大悲おおもいが働いているといわれています。
それゆえ「念仏せよ」と如来がおおせられることは「わたしを親とよべ」ということであり、わたしが念仏するということは、
自身が一子のごとく念じられていることを聞いてみて親をよぶ慶びの声であり、広大無辺な阿弥陀仏の徳をたたえる讃仏の声でもあります。
同時にまた仏子と知らされながら、およそ仏の子らしからぬ浅ましく愚かなわが身を恥じる懺悔(さんげ)の念仏でもあります。
▼摂取不捨の利益にあずかる
こうした人間の思いを超えた悟りの世界から、大悲をこめて招喚したもう本願のみことばを信じ、
如来をみ親とよばせていただこうというおもいがおこるとき、すでにわが身は如来の親心の中に抱かれてある身であることを知れと、
親鸞聖人はおおせられるのです。それが
弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて、往生をばとぐなり、と信じて、念仏もうさんとおもひたつこころのおこるとき、
すなわち摂取不捨の利益にあづけしめたまふなり。
というみことばなのです。「凡夫の思いを超えた阿弥陀仏の本願の御はからいに救われて、往生をとげさせていただくことであると信じ、
念仏を申そうと思いたつ心がおこるそのとき、すでに阿弥陀仏は大悲の光明のなかにおさめとりたまい、
決して見捨てたもうことのない利益をおさずけくださっております。」というのです。
本願を信じ、おおせのままに念仏させていただこうとおもう心のおこるとき、即座に摂取不捨の利益があたえられるといわれましたが、
このように阿弥陀仏の救いを
「摂取不捨」ということばであらわされたのは『観無量寿経』でした。
『観経』の第九真身観に、阿弥陀仏は全身から無量の光明をはなって十方の世界を照らし、
「念仏の衆生を摂取して捨てたまはず」と説かれています。この経文は、ずいぶんたくさんの人びとに阿弥陀仏の救いを知らせ、
深いやすらぎと喜びを与えていきました。
■さわやかな光をあびて‥‥‥
善導大師は「光触(こうそく)かぶるものは、心退(こころしりぞ)かず」といい、念仏の行者は大悲の光明に照らし護られて、
浄土に向かって不退転の歩みをつづけさせていただくのだとよろこばれています。
法然聖人が、この経文の心を
月かげのいたらぬさとはなけれども
ながむる人のこころにぞすむ 『続千載和歌集』
と詠まれたことはよく知られています。
さわやかな秋の月は、その光をすべての人のうえにわけへだてなくそそいでいますが、
光を背にして大地にはいつくばるものは光の中にありながら光にあうことができません。ただわが身の黒い影におびえるばかりです。
闇を背にして月を仰ぐ人だけがさわやかな月の光を全身にあびて、心の底まで、澄みわたっていきます。まさにそのように、大悲の光明は、
万人を平等に照らしたもうが、それを聞きひらいて、われもまた光明のなかにあり、
とみ教えをあおいで念仏するもののみがさわやかな光のうちに人生を全うすることができるといわれるのです。
▼愛と憎しみにとらわれている愚かなわたしだからこそ
源信僧都は『往生要集』のなかで
『観経』の「光明遍照十方世界念仏衆生摂取不捨」のこころをわが身のうえにいただいて
われもまた彼の摂取のなかにあり、煩悩眼(まなこ)を障(さ)へて見てたてまつることあたはずといへども、
大悲、ものうきことなくして、常にわが身を照らしたまふ。
と深い感動をこめて述懐されました。
妄想(もうそう)にくらまされ、愛と憎しみの情念に翻弄(ほんろう)されている愚かな身に、真実をみる智慧の眼はありません。
凡夫の眼には、ただみずからがえがきだした愛と憎しみの対象しか見えないのです。それゆえ迷いはいよいよ深まり、
罪障(ざいしょう)はいよいよ重くならざるをえません。
如来の大悲心とは、こうした愚かな凡夫を限りなくいたみつつ、どうぞ真実に気づいてくれよと願いたもうた心です。
如来とは、如来という真実のみ親をみることのできないものを、かたときも眼をはなさず、身まもりつづけていたもう方をいうのです。
そして凡夫とは、如来を見る智眼(ちげん)をもたないがゆえに、つねに大悲のまなざしをそそがれ、暖かく身まもられているものだったのです。
わたしは見る主体であり、知るものであると思っていましたが、本当は、如来によって見まもられている客体であり、
知りつくされている救いの正客だったのです。
ですから、如来を見ることができないことを悲しむよりも、見まもられていることを聞いてよろこぶべきなのでしょう。
■すでに大悲の光明の中にあった‥‥‥
源信僧都は『観経』の経説にしたがって、如来をまのわたりみたてまつろうとして、精魂をかたむけて修行されたのですが、
ついに如来を拝見することができず、自身の煩悩、罪障の深さをもてあまされていたにちがいありません。
そのとき「念仏衆生、摂取不捨」という経文が、まったく新しい視野を開いてくれたのです。仏をおもい、
み名を称えているわたしはすでに「念仏の衆生」ではないか。してみれば「念仏の衆生を摂取して捨てず」とのおおせは
「そなたはすでに大悲の光明のうちに抱きとられているのだよ」とつげられていることではないか。
そう気づかれたとき、豁然(かくぜん)として心がひらけ、「我もまた彼の摂取のなかにあり‥‥‥」と口ずさんでいかれたのでしょう。
親鸞聖人は、この源信僧都の領解に深く感動されたらしく『正信偈』や『尊号真像銘文』をはじめ諸所に引用されていますが、
ことに、『高僧和讃』には、
煩悩にまなこさへられて
摂取の光明みざれども
大悲ものうきことなくて
つねにわが身をてらすなり
と讃詠されたのでした。
■あみだ―救いをつげるみ名
『浄土和讃』「弥陀経讃」のはじめに
十方微塵世界の
念仏の衆生をみそなはし
摂取してすてざれば
阿弥陀となづけたてまつる
と讃詠されています。十方世界の、どこにいて念仏するものであっても、如来はお見のがしなくみそなわし、
その大悲の光明のなかに摂め取って決して見捨てたもうことがないということをわたしどもにも知らせるために
阿弥陀仏と名のっておられるのだというのです。
もともと「阿弥陀」とは、アミターバ(無量光)とアミターユス(無量寿)の徳をもった仏という意味ですが、
その無量光(はかりしれぬ智慧の光)のはたらきを「摂取不捨」とあらわされたのですから、阿弥陀仏とは「摂取して捨てない(必ずたすける)」
というたしかな救いの誓約をあらわすみ名であるといわれるのです。蓮如上人が「阿弥陀といふ三字をば、をさめ・たすけ・すくふとよめるいはれ」
ありといわれたのもこれをうけられたのでしょう。南無阿弥陀仏と称えていることは「そなたををさめ、たすけ、すくう」
とつげまもう如来のお名のりを聞いていることになるのです。
■逃げまどうものをどこまでも
「もののにぐるを、おはへとるなり」といわれたものほど、阿弥陀仏の救いのありさまをあざやかにいいあらわされた言葉はありません。
念仏の衆生が摂取されるといえば、念仏という善根を積んで仏に近づいていく善人を、
仏はその功徳に応じて光明をはなって救いとりたもうことであると理解するのが普通でしょう。
しかし念仏のみ教えに遇いながらも、なお愛と憎しみの情念にふりまわされて、煩悩の大地をはいずりまわっているようなわたしの現実は、
如来に向かうどころか、背をむけ、顔をそむけて逃げまどうているようなありさまだといわねばなりません。
こうした「逃ぐるもの」を、どこまでも追い求め「われに帰せよ」とよびさましつつ、
大悲のなかに包摂していかれるありさまを「ものの逃ぐるを追はえとるなり」といわれたのでした。
こうしたダイナミックな摂取のはたらきこそ、罪業の凡夫を救おうと願い立てられた本願のはたらき、すなわち本願力なのです。
摂取不捨の本願力こそ、逃げまどうわたしを念仏者たらしめた力でもあるのです。それゆえ本願を聞いて信順し、念仏しているものは、
すでに摂取不捨の本願力のはたらく領域に入らしめられているといわねばなりません。
▼正定聚ーこの世にありつつ浄土の聖者の仲間に
そのことを親鸞聖人は『御消息』のなかに
真実の信心の行人は摂取不捨のゆゑに正定聚(しょうじょうじゅ)の位に住する。
このゆゑに臨終まつことなし、来迎たのむことなし、
信心のさだまるとき、往生またさだまるなり。 「御消息」
といわれました。
ここにいわれる
「正定聚」とは、「正しく悟りの世界に生まれ,仏陀となることに決定している聖者の仲間」ということです。
本願を信じ念仏する行者は、すでに如来に摂取されているから、もはや迷いの境界に退転することなく、確実に仏にな道を歩ましめられている。
それを正定聚の位に入らしめられた、とよろこばれているのです。
念仏者になったとしてもこの世にある限り、愛憎の煩悩に支配され、煩悩に束縛されている凡夫でしかありませんが、
本願を信じ念仏するということは、本願の秩序にしたがい、如来の支配下に包摂されているすがたでもありますから、この世にありながら、
如来の眷属たらしめられているといういわれもあります。
親鸞聖人は、信心の業者は、この世にありながら大会衆の数に入るといわれました。
大会衆とは、浄土にあって如来の説法の会座(えざ)に集まっている聖者たちのことです。
煩悩の凡夫と、清らかな聖者(しょうじゃ)とは天と地のちがいがありますが、阿弥陀仏の願いを聞いて感動し、
阿弥陀仏というみ名にこめられた摂取不捨の仏心を聞いて喜ぶという点では共通しています。
ともに阿弥陀仏から直々の説法を聴聞しているということですから、本質的には同じであるといえましょう。
念仏の行者が摂取不捨の利益にあずかるとは、そうしたすばらしい精神の領域を開かれることを意味していました。
◇弥陀の救いをさまたげるほどの悪はない
前号では、阿弥陀仏の誓願のみことばを真実と受け入れ、そのみことばのままに、
阿弥陀仏のみ名を称えようとするところに開かれてくる世界―についてうかがいました。
今号では、そのように阿弥陀仏の誓願によって救われていく人というのはいかなる人なのか、そしてまた、
その救いとはいかなるかたちで実現されていくものか、ということについて述べていただくことにいたします。
▼だれ一人として、もれることなく救われていく教え
『歎異抄』の第一条第二段には、
弥陀の本願には、老少・善悪のひとをえらばれず、ただ信心を要とすとしるべし。
そのゆゑは罪悪深重(ざいあくじんじゅう)・煩悩熾盛(ぼんのうしじょう)の衆生をたすけんがための願にまします。
といわれています。
ここには、浄土真宗の特色である大悲平等の救いと信心を要とする旨があざやかに示されています。
阿弥陀仏のみこころのまえには、年老いた人も、若者も、善き人も、悪しき人もわけへだてはありません。
大空がすべてを包むように、大地が淨穢(じょうえ)をへだてずに乗せているように、
阿弥陀仏の本願の大悲は、万人をわけへだてなく包んで安住の場を与え、愛と憎しみの煩悩の消えた、
清らかな涅槃の浄土に入らしめるように念じたもうているといわれるのです。
それはまさに、大乗の極致をあらわしているといえましょう。
仏教には自分だけの悟りをめざす小乗と、すべての人々とともにさとりを実現しようとする大乗とがあります。
乗とは乗物(船)ということで、愛と憎しみと愚かさの濁流を乗りこえて、
さとりの彼岸へと人びとを導いていく仏の教えを乗物にたとえたものです。
船には一人乗りの小さい船と、無数の人びとを乗せて向こう岸へ送りとどける大きな船とがあるように、
仏の教えにも、大乗と小乗があるといわれているのです。
大乗の大には、大と多と勝の意味があるといわれています。
大とは広大無辺ということで、万人を平等に乗せて彼岸へ渡す、かぎりなく広く大きい普遍的な教えということです。
多とは、はかりしれない徳をもっているということであり、
勝とは、もっともすぐれた教えという意味です。
大乗とよばれるなかにも、『法華経(ほけきょう)』・『華厳経(けごんきょう)』『大日教(だいにちきょう)』などにとかれる自力の大乗と、
『大無量寿経』に示された本願他力の大乗があります。
自力の教えは、理念としては、すべての人びととともにさとりをめざすといっても、現実には、よほど強い意志と、
強靱(きょうじん)な体力と透徹(とうてつ)した知力を持った、ほんのわずかな修行者しか歩むことができない、狭くけわしい道なのです。
それにひきかえ、阿弥陀仏は、平等の大悲をもって立ちあがり、善人も悪人も、賢者も愚者も、
老人も若者も、出家も在家も、男も女も、一人ももれなく乗せて彼岸へ至らしめる南無阿弥陀仏という大願の船を完成し、
「これに乗れ」万人をよびたもうていると説かれたのが、『大無量寿経』の
本願他力のみ教えでした。
それゆえ、曇鸞大師(どんらんだいし)はこの教えを「上衍(じょうえん)の極地(ごくち)(大乗仏教の極地(ごくち))」とたたえた、
親鸞上人も、真の大乗とは、「誓願一仏乗(せいがんいちぶつじょう)」であるといわれました。
阿弥陀仏の誓願の救いこそ、万人が等しく仏陀にならしめられる唯一無二の教えであると讃仰されているのです。
▼「老少、善悪のひと」とはだれのことか?
ところで、
「老少、善悪のひとをえらばれず」というと、ともすれば、あの老人も、この若者もとか、あの悪い人もこの善い人も、
というふうに老少、善悪をそとに見て、そのように考えている自分自身は救いの場からはみだしている、ということがあります。
確かに老少、善悪をえらばないということは、救いの普遍性をあらわしていますが、
それはじつはわたし一人の救いを確証してくださる教語として、自身のうえにいただくべきでありましょう。
その意味で、若いときのわたしも、年老いたときのわたしも、善い心のおきているときも悪い思いにけがれはてているときのわたしも、
わけへだてなく救うと仰せられているのだとわたしはいただいています。
若いときは救われても、年老いたならば見捨てられるようでは、老いの寂しさと悲しみをもてあますことになりますし、
老人ならば救わないような宗教ならば、若者の悩みを導くことは出来ません。若者と年寄りとは一人の人生の歴史なのです。
「老少をえらばず」との仰せをたまわりますから、如来の大悲は、わたしの老少を貫いて、全人生を支え、
そのときどきの悲しみと惑いを導き、慰めたもうことを知るのです。
善人、悪人といっても、実際には自分自身のうえに善、悪さまざまな思いと行動が、
ひるがえりながらつづいていく日常の生活のほかにありません。この世に生きているかぎり、
善ばかりの人とか悪ばかりの人というものはないでしょう。ときにはすばらしいことを思ったり、行ったりすることもありますが、
その全体を帳消しにしてしまうような悪いことをいったり、行ったりするのが、私どもの弱く悲しい現実なのです。
仏法を聞いて感動し、涙を流すこともありますが、いくら聴聞しても、なんの感動もないときもあります。
ところが浄穢、善悪はわがことでありながら手のつけようもないような深みをもっています。
美しく立派な心境になっているときは救われるのが、妄想にけがれたみにくい心情のときには救われないといわれるならば、
私に救いはないでしょう。「善悪の人をえらばず」と仰せられるので、善いときは善いまま、悪いときは悪いままに
「おんたすけ一定」と安心せしめられるのです。
親鸞聖人はお手紙のなかで、
わが身のわるければ、いかでか如来迎へたまはんとおもふべからず、凡夫はもとより煩悩具足したるゆゑに、
わるきものとおもふべし。またわがこころよければ往生すべしとおもふべからず、……このゆゑに、よきあしき人をきらはず、
煩悩のこころをえらばず、へだてずして、往生はかならずするなりとしるべし 『御消息』
とさとされています。
まことにわがこころが善くて救われるのではありません。如来の本願力によらねばどんな善人も涅槃の浄土にはいたれないのです。
またわがこころが悪いから救われないのではありません。如来は無限の救済力をもって、
罪悪深重の凡夫をさわりなく救うと仰せられているのです。それゆえわたしどもは、わが身の善し悪しをこざかしくはからわず、
ただ如来のおんはからいに身をうちまかせるばかりです。
善悪をこえて万人をへだてなく救うと仰せられる不可思議の誓願ありと聞けば、ただ素直に信順することがなによりも肝要です。
それゆえ
「弥陀の本願には、老少、善悪のひとをえらばれず、ただ信心を要とすとしるべし」と仰せられたのです。
▼一切の人びとをわけてだてなく救うという願い
法然上人は『選択集』本願章に、阿弥陀仏が易行の念仏を選び取られたありさまをのべて、
万人をへだてなく救おうとおぼしめす平等の大悲は、
自力の難行から見放された愚悪な庶民大衆に焦点をあわせつつ選択せられたといわれています。
知者も、愚者も、強者も、弱者も、富者も、貧者も、平等に救いためには、知者よりも愚者に、
強者よりも弱者に焦点を合わせて救いの法が選び取られなければならないというのです。
たしかに若くして健脚のものと、年老いて足の不自由なものを、わけへだてなく同時に大阪から東京へつれていこうと思えば、
足の弱い老人を標準にして道を選ばなければなりません。もちろんそれはめいめいの脚力にたよる道であってはなりません。
そこで列車に乗せてつれていくことにすれば、足の強弱にかかわりなく、平等に目的地につくことができましょう。
ちょうどそのように阿弥陀仏の大悲は、社会的にも、個人的にも、精神的にも、肉体的にも、
一番弱い立場におかれて苦しみ悩んでいるものに救いの焦点を定め、本願他力の道を選び取り、万人平等の救いを実現していかれたわけです。
そのことを
「そのゆゑは、罪業深重・煩悩熾盛の衆生をたすけんがための願にまします」といわれたのです。
▼わたしのこころの善し悪しに左右されない
『歎異抄』第一条は、
しかれば本願を信ぜんには、他の善も要にあらず、
念仏にまさるべき善なきゆゑに。悪をもおそるべからず、
弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑにと云々。
とむすばれています。
罪悪深重(ざいあくじんじゅう)の凡夫の救いに焦点をあわせながら、老少・善悪をへだてなく迎え取ろうと願われた阿弥陀仏は、
そのみ名にその徳のすべてをおさめて、万人にほどこし、
「わが真実なる誓願を信じ、わが名を称えよ」とよびたもうています。
それゆえ仏の本願を信ずるものは、仰せのままに念仏すべきであって、往生のために他の善を必要としません。
如来よりたまわった本願の念仏にまさる善はないからです。また悪もおそれるべきではありません。
本願の無碍の救いをさまたげるほどの悪はないからだといわれるのです。
ここに
「念仏にまさるべき善なきゆゑに」といわれるのは、本願念仏の絶対性をあらわしており、
「弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑに」とは、本願力の無碍性を示されたものです。
本願を信じ、念仏をもうすものは、善悪をもって人を批判する倫理的な領域をこえて、
善もほしからず、悪もおそれなしといわれるような絶対無碍の領域に心がひらかれていきます。
それは阿弥陀仏が大悲の智慧をもってみそなわす世界であるといえましょう。念仏者は、わがこころの善し悪しにまどわされることなく、
善いときも、悪いときも、暖かく見守ってくださる如来の大悲のまなざしのなかに、絶対の安住の地を見いだすのです。
覚如上人は『口伝鈔』第四条に同じ意味の聞き書きをのべたあとに、
しかれば機に生まれつきたる善悪のふたつ、報土往生の得ともならず失ともならざる条勿論(じょうもちろん)なり。
さればこの善悪の機のうえにたもつところの弥陀の仏智をつのりとせんよりほかは、凡夫いかでか往生の得分あるべきや。
と仰せられました。
わたしどもは、善き縁に会えば善いことをし、悪い縁にあえば悪いことをしてしまうような定めなき性分をもって生まれてきています。
しかしわたしのうえの善悪は、阿弥陀仏の浄土に生まれるためには、役にもたたねば、邪魔にもならないことはいうまでもありません。
だから、善かったり悪かったり、定めなくかわっていくこの身の上に与えられた、阿弥陀仏の智慧の名号をたのみとするほかに、
凡夫のどこにも往生できるような値打ちはないといわれるのです。
▼名号のすばらしいはたらき
阿弥陀仏が、万人を救うための行法として選び取られ南無阿弥陀仏は、(なもあみだぶつ)は、
だれでもがいただける至極(しごく)の易行(いぎょう)であるとともに、阿弥陀仏のお徳のすべてが込められた最も優れた行であり、
無上の功徳(くどく)であると、法然上人は仰せられた。それをうけて親鸞聖人もまた名号の徳をたたえて
「万行円備の嘉号」とか、
「真如一実の功徳宝海」などと口をきわめて讃嘆されています。
仏になるために必要なあらゆる行の徳をまどかにそなえたすばらしい名号は、
それをいただくものを必ず仏にならしめるはたらきをもっております。こうして本願の名号をいただいた行者は、
無上の功徳を身に宿されたものであり、生死の惑いをこえて涅槃のさとりを極める身にならしめているのですから、
もはや他の善根功徳を必要としないことはいうまでもありません。
そのこころを『正像末和讃』には、
五濁悪世(ごじょくあくせ)の有情(うじょう)の、
選択(せんじゃく)本願信ずれば
不可称不可説不可思議の、
功徳は行者の身にみてり
と讃詠されたのです。
▼いかなる罪も清らかな仏徳に
つぎに
「悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑに」といわれたのは、
阿弥陀仏の自在無碍(じざいむげ)の救うはたらきを表された言葉です。
阿弥陀仏とは尽十方無碍光如来であると天親菩薩は仰せられました。十方世界に生きとし生けるすべてのものを包摂(ほうせつ)して、
一人ももらさず、いかなる罪障にも邪魔(じゃま)されず、まるで光が闇を破るように、さわりなく救いたもう大悲の智慧の如来であることを、
この名は告げております。親鸞聖人は晩年、とくにこの十字の名号を通して如来の徳を味わわれたようで、
いたるところにくわしい註釈をほどこされています。
極重の罪障を転じて、清らかな仏徳に転じて如来の大悲の智慧のはたらきは、人間の思慮分別のおよぶところではありませんから、
この如来を不可思議光如来ともいいます。こうして南無阿弥陀仏(帰命尽十方無碍光如来、南無不可思議光如来)というみ名を聞き、
そこに告げられている自在無碍の救いを聞きひらけば、
おのずから「悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑに」という不動の信が生まれてきます。
■わたしの愚かな一人相撲
鳥取県の山根という山村に足利源左という妙好人が住んでいました。その近くの用ヶ瀬町に正覚寺という寺があり、そこの坊守は、
熱心な聞法者でしたが、どうしても如来のお救いがうけとれず、長いあいだ悩んでいました。そんなある日、
たまたま源左が正覚寺へ参詣にきたので、さっそく坊守は自分の苦しい胸のうちをうちあけて相談しました。
「如来さまのお慈悲がわからず、後生が苦になってなりません。どうしたら安心ができましょうか。」
すると源左は、
「奥さん、往生はいかがかと、後生に不審が起きたら、だれに相談するのでもない、なによりも第一に親さまのまえにでてみなせ、
親さまは、どれで悪い、とおっしゃらんけえの。」
この一言が坊守の胸にひびきました。
「おお、そうであったか、親さまは、どれで悪いというようなお方ではなかったのだのう。やれやれなあ、
わたしは愚かな一人相撲をとっていたことがようわかりました。こんな愚かなわたしを助けてくださるとは、もったいないかぎりじゃのう。」
と涙ながら感謝する坊守の肩をたたいて源左は、
「奥さん、ながい辛抱でしたなあ、もうようございますぜ。」
といっしょにお念仏しながら喜んだといいます。
「どれで悪いとは、おっしゃらんけえのう。」
という一言こそ、
「悪をもおそるべからず、弥陀の本願をさまたぐるほどの悪なきゆゑに」という無碍の救いのいわれを、
みごとにいい切っております。
梯 実円 先生